「海外に住んでいれば、子どもは自然にバイリンガルになる」と思っていませんか?
実は、これは多くの方が抱く誤解です。

私自身、イギリスに移住した当初(子どもが生まれる前)は「英語環境にいれば、勝手に子どもはバイリンガルに育つ」と信じていました。
ところが、現実はそう簡単ではありません。
むしろ、海外に住んでいてもバイリンガルを育てるって凄い大変な努力と継続が必要だったんだ!とビックリ&がっくりしたというのが正直なところです。
バイリンガルを育てるためのリアルな情報を集めていくうちに、
子どもは成長するにつれて、自分が使いたい言語を選んでいく、ということを目の当たりにしたからです。

子どもはまず、一緒に過ごす時間が長い人の言葉を第一言語として学びます。多くの場合はお母さんです。そして成長するにつれて、環境や周囲の言語の割合によって、使う言語を自分で選ぶようになります。
例えば、東京に住む家庭で、お母さんが関西弁、お父さんが標準語だとします。
お母さんと過ごす時間が長ければ、自然に関西弁が強くなる傾向があります。その後、幼稚園に通えば標準語のアクセントが混じり、青森に引っ越せば津軽弁の影響を受けるかもしれません。年齢が上がれば、逆に自分の意思で青森に居ても標準語を選んで話すこともあるでしょう。
英語でも同じです。まず一緒にいる時間が長い人の言葉が第一言語になり、その後は環境や本人の意思によって変わっていきます。子どもの頭は本当にスポンジのように、周りの言葉をどんどん吸収していき、必要に応じて取捨選択していきます。
その為、英語圏に住んでいて幼少期はバイリンガル(2か国語)だった子でも、成長するにつれてどちらか一方を選んで話すようになることは多いにあります。
特に5歳を過ぎると、小学校が始りますので英語圏に住んでいる子どもの日本語力はあっという間に弱くなることが多いです。小さい頃はバイリンガルだったのに、いつのまにか日本語が話せなくなってしまう。これは日本語に限らず、どの言語でも同じ現象が起こるようです。(私の周りの友人、知人の子供さん達は英悟オンリーになってしまった…という実例が沢山あります。)

親が意識して環境を整えない限り、どちらかの言語が極端に弱くなることは珍しくありません。
つまり、「住んでいる場所」だけでバイリンガルになるわけではない、ということです。
日本語も英語も流暢に話せるようになるのは、親と子供の努力と継続の賜物なんだ、ということを目のあたりにした私は、色々調べた結果、子供の頃はリスニングに力を入れる事にしました。
おかげで子供達は10歳と12歳になりましたが、今でも日本語はとても流暢に話せます。
アクセントも普通の日本の子供達と変わらないので、日本に一時帰国した際、「普段はイギリスに住んでいる」と伝えると、ほとんどの場合ビックリされます。
「日本に住んでるのかと思った。どうやってそんなに流暢な日本語を話せるようになったの?」と聞かれるほどです。

1. 我が家の実例:イギリスで二児をバイリンガルに育てるまで
私がイギリスに来た時の英語のレベルは日常会話ができる位でした。
夫はイギリス人、以前日本で英語の先生をしていた経験もありますが、日本を離れて数十年。子供が生まれる前はあまり日本語は話せませんでした。レベルでいうと超ビギナーレベルです。
私と夫の会話は日本語と英語が混ざっていて、どっちもどっち、というようなコミュニケーションレベルでした。
そんな我が家は、子供が生まれる時に思い切ってリスニングに力を入れる!というルールを決めました。
- 音楽を聴く時は日本語の子ども向け歌を繰り返し聞く
- 毎晩日本語の絵本を3冊読み聞かせする
- リスニングに集中することを一番に心がけ、読み書きは力を抜く
- 誰かと一緒にいても子供には日本語で話す
- イギリスのテレビではなく、YoutubeやDVDを使って動画はすべて日本語のものを選ぶ
当時、周りの人からは「そんなことして義理のご両親と関係悪くならない?」「旦那さんが日本語が分からずに家庭内でストレスを感じない?」「英語が話せなくなるんじゃないの?」などなど、周りから心配されたこともありました。
正直、最初は私も心配でした(笑)。なぜなら、子供たちはイギリスに住んでいながら小学校に上がる5歳になるまで英語をほとんど話せなかったからです。
※幼稚園は週に15時間、3歳と4歳の二年間しか通いませんでした。その間も英語がほとんど出てきませんでした。
私は子供達の幼稚園の先生や義理の両親には「バイリンガルになるようにリスニングに力を入れています。その為子供達には日本語のみで話しかけてます。英語がまだ苦手ですが理解して頂けたら嬉しいです。」と伝えていました。
その為周囲の人はバイリンガル教育の難しさを理解してくれて、子供達にも私にも協力的に接してくれました。
バイリンガルならではの笑えるエピソードも沢山あって、今では良い思い出になっています。
義理の両親との心温まるエピソード
子どもが生まれた時、私は義理の両親に「子どもたちには“じーじ”と“ばーば”と呼ばせたい」とお願いしました。
すると義理の父母が笑いながら、こう言ったんです。

「じーじ(Gee Gee)は英語で“馬”の意味だし、ばーば(Baa Baa)は羊の鳴き声だから、僕たち動物になるんだね!それは面白い!
こうして笑いながら受け入れてくれたおかげで、子どもたちは今も自然に日本語で「じーじ」「ばーば」と呼んでいます。
バイリンガルを育てるためには、親だけじゃなく、周りの協力や理解も大事だなと心から感じています。
英悟環境でも、いかに日本語を使える環境にするかを意識すれば、バイリンガルに育つ可能性は高まります。
これは、日本在住でも同じことが言えます。子供に英語を話せるようになって欲しい場合はリスニングにまずは力を入れる事をお勧めします。それも、年齢は早ければ早い方がいいです。読み、書きは後でも大丈夫です。リスニングをしっかりしていれば、後から追いついてきます。
英語を生活の中で使えるように、そして継続できるように周りの環境を作ることがポイントです。
2. バイリンガル育児のカギ「コップの法則」
なぜ最初はリスニングなのか。
私はバイリンガル教育をする時のコップの法則を知っていました。だから、兎にも角にも耳から育てた方が良い、と考えていました。
バイリンガルは頭の中に日本語と英語、二つの“コップ”を持っている、と言われます。
それぞれのコップがその言葉で満たされると、その言葉が自然に口からあふれ出します。話し言葉の発達は、コップにインプットされる言葉の量で決まると言われているそうです。

バイリンガル環境の子どもが「発語が遅い」と言われることが多いのですが、それはコップがまだ満たされていないからなので、過度に心配せず、親が言葉でコップを満たす手助けをすることが大切なんだそうです。

私の子どもたちも5歳までイギリスに住んでいましたが、英語はほとんど話せませんでした。
日本語のコップは満たされていたので、「英語のコップがまだ足りないだけ」と認識していました。
その後小学校に入ってから、英語のコップがどんどん満たされ、あっという間に英語も話せるようになりましたよ。
日本在住でもできる!家庭での英語環境づくりのヒント
- 幼児の英語の歌を聴く
- 毎晩英語絵本の読み聞かせを聴く
- ディズニー映画を英語で観る
- 日本のアニメを英語バージョンで観る
どれも今日から始められることばかり。お金をかけなくてもできます。まずは耳を育てましょう!
まとめ。リスニングに注力し、周りの環境から固めていく
子どもがバイリンガルに育つかどうかは、住んでいる場所だけで決まるものではありません。
「今から何をするか」で未来が変わります。
赤ちゃんが話せるようになるのは、沢山聞く練習をしているからです。コップに沢山の言葉が入れば、子供はどんどん話せるようになる!という意識で接してみてください。
バイリンガル教育では、言葉の遅れが出る事がありますので、焦りや不安を感じる事もあるかもしれません。
ですが安心してください。子供の頭はスポンジのようにどんどん吸収しますので、後で追いつきますので大丈夫です!子供の可能性を信じて見守ってあげてください。
我が家が取り入れて効果があった習慣は、どれも今日から始められるものばかりです。
ぜひ、ご家庭に合う方法を試してみてください。
そして、忘れないでほしいのは、親だけじゃなく周りの協力や理解も大事ということ。うちの義理の両親のように笑って受け入れてくれる存在がいると、子どもも安心してバイリンガルの世界に飛び込めますよ。
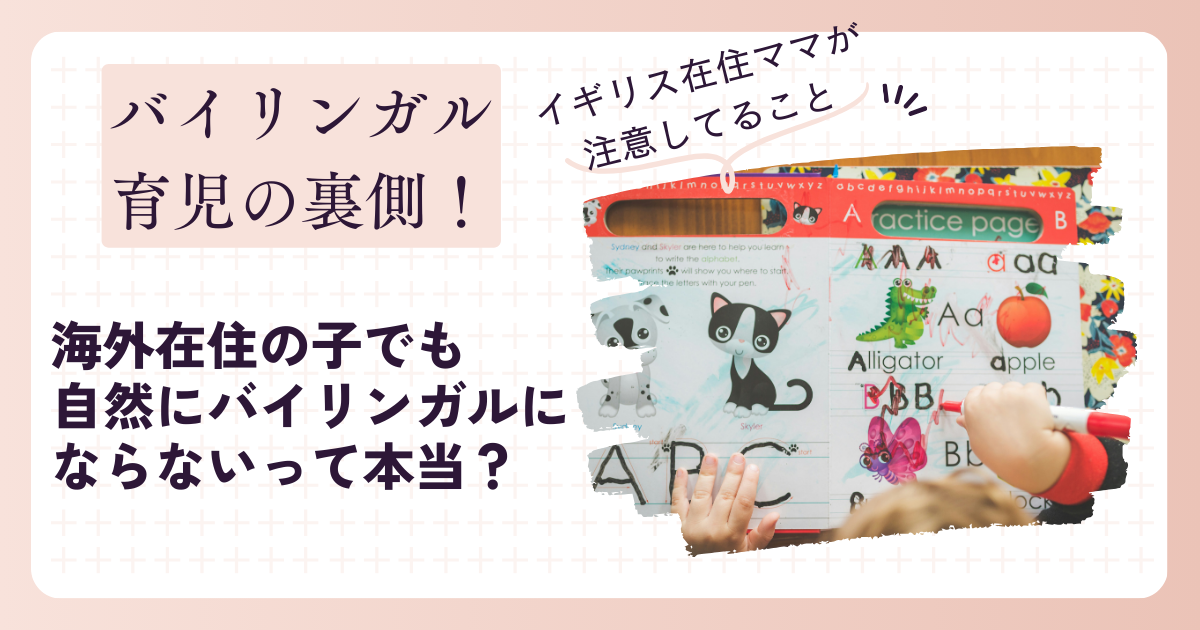
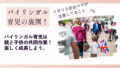
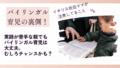
コメント